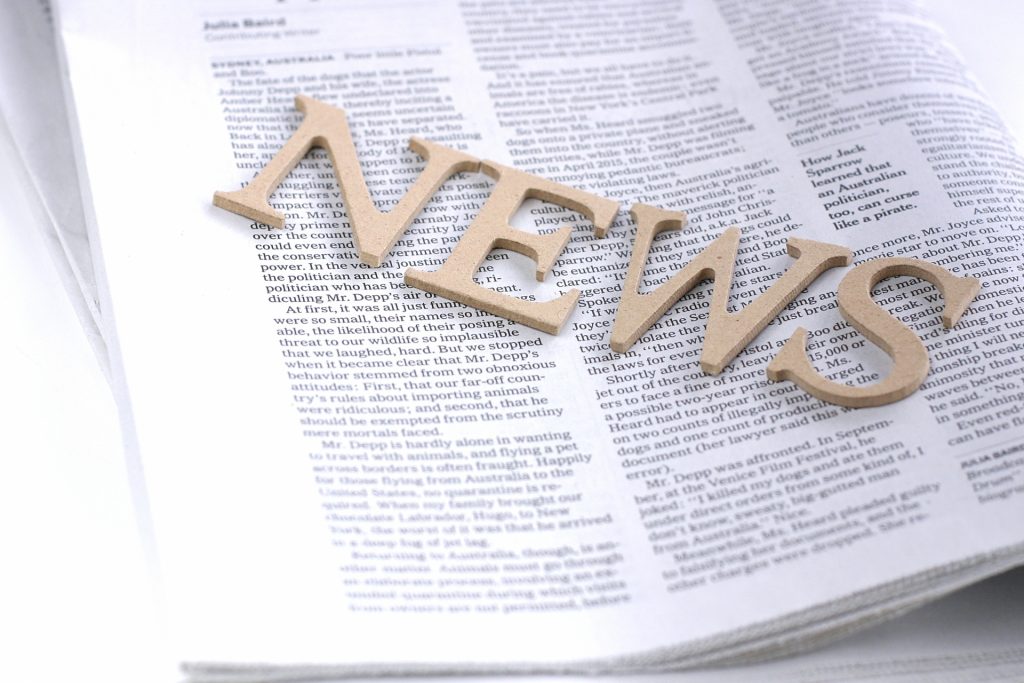2021年は大変お世話になりました。
キャプティブ研究所も一般社団法人化し、より公的な活動をする土台が整った1年でした。毎月多くのお問い合わせをいただき、年間100件に近い企業様へのアドバイスや、ハワイとラブアンを中心とした設立も行わせていただきました。
まだまだ中堅、中小企業様への認知度は低く、活用事例も数少ないものになりますが、徐々に増えてきている実感があります。
リスクファイナンスという王道の使い方もそうですが、やはり「資産税をどう回避するのか」「どう資産を守るのか」への経営者様の関心度が非常に高いです。特に今年は政権が変わり、いよいよ内部留保金課税の議論も加熱してきております。
そして、コロナに対する財政出動による反動での増税は逃れられないものになります。日本の財政状況も悪化の一途をたどっており、今後益々リスク分散のために海外を活用した資産保全は求められます。
キャプティブ研究所として、来年も多くの中堅中小企業様に質の高い情報をご提供することに注力し、設立もさらに増やしていきたいと思っております。
来年も、一般社団法人キャプティブ研究所を宜しくお願い申し上げます。
最後になりますが、皆様のご多幸を祈念して本年の最終メルマガにさせていただきます。
所長 足立 哲真